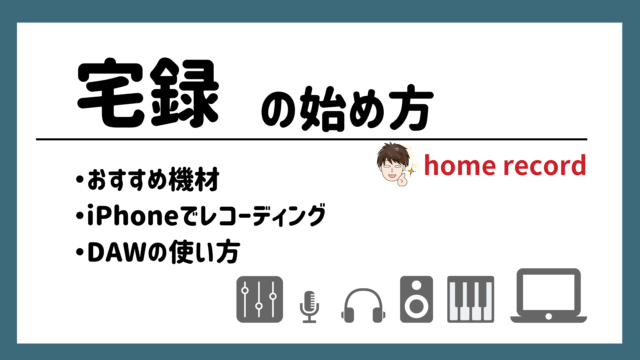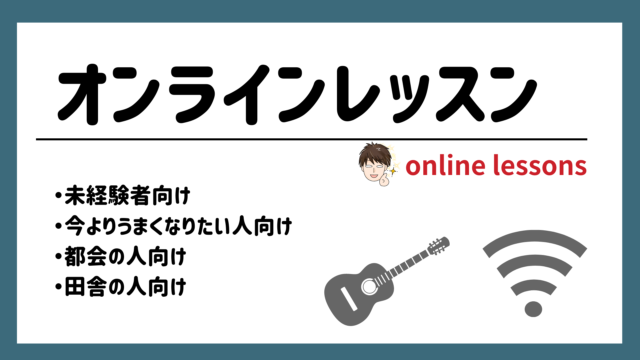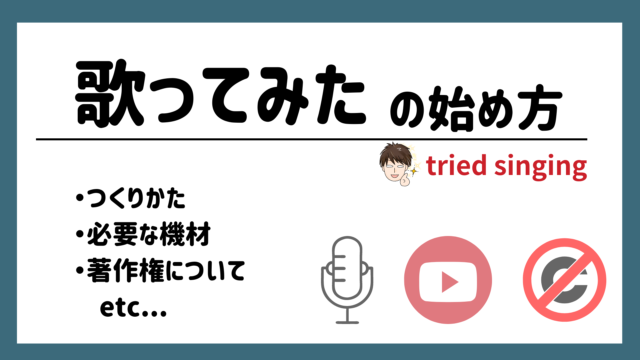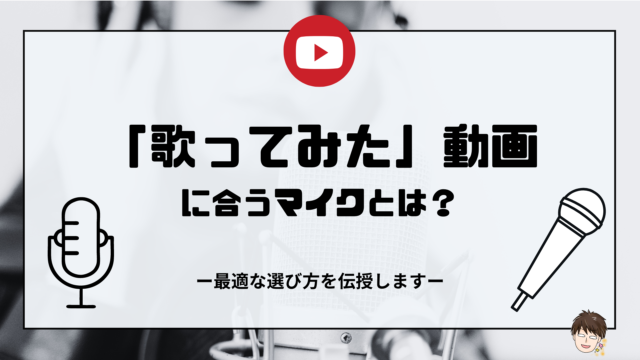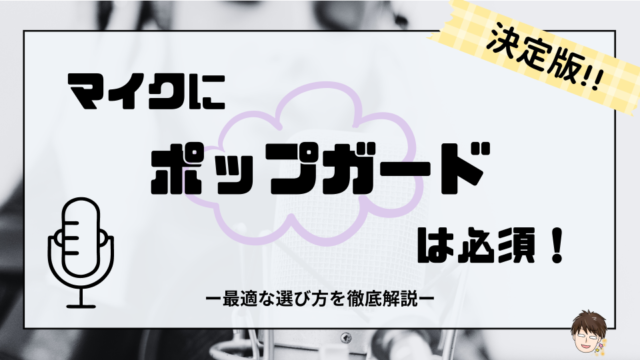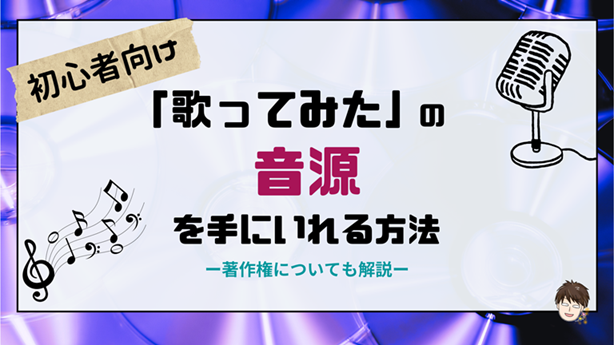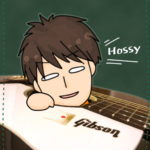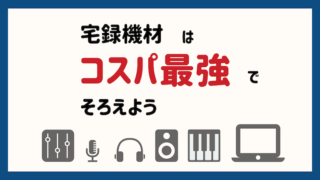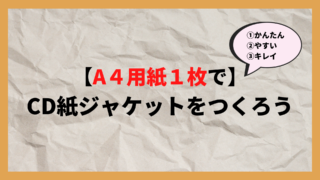歌をもっと表情豊かにしたい。。
こう考えるとき、多くの人が憧れるのが「ビブラート」です。
声に揺らぎを与えて感情を表現できるこの技術は、歌唱力を高めたい人にとって欠かせない要素です。
しかし「ビブラートの出し方」が分からず、自己流で挑戦してみても「上手くかからない」「不自然になってしまう」と悩む方は少なくありません。
本記事では、初心者でもわかりやすいように、ビブラートの出し方の基本・正しい練習方法・おすすめの練習曲までを徹底解説します。
自宅でできるトレーニングを取り入れれば、無理なく自然なビブラートを身につけることができます。
呼吸法や姿勢のコツを押さえて、美しいビブラートを手に入れましょう。
» 自宅でできる!歌がうまくなる具体的な方法を解説
ビブラートを出すための基礎知識

ビブラートは、歌声に深みと表現力を与える大切な技術です。
適切に使うことで、声がより豊かに響き、聴き手に心地よさや感動を与えることができます。
ただし、ビブラートの出し方を間違えると「不自然」「しつこい」と感じられてしまうこともあります。
自然で無理のないビブラートを心がけることが大切ですが、速さや深さは曲のジャンルや歌う人のスタイルによって変わります。
歌の経験と「コツ」を掴むことでビブラートへの理解が深まります。
横隔膜・喉・口腔の役割
ビブラートを自然に出すためには、横隔膜・喉・口腔の3つが重要な役割を担っています。
- 横隔膜:呼吸をコントロールし、声を安定させる役割を持ちます。息の流れを調整することで、ビブラートの速さや深さをコントロールできます。
- 喉:ピッチ(音の高さ)の微細な揺らぎを生み出し、ビブラートの細かい調整を担います。
- 口腔:音を共鳴させ、響きや音質を整える部分です。口の形を変化させることで、ビブラートの質感や色合いを調整できます。
この3つがバランスよく協調することで、無理のない自然なビブラートが生まれます。特に横隔膜と喉の連動が安定感を生み、口腔のコントロールが音色を洗練させます。
横隔膜・喉・口腔の役割を理解して正しく使い分けることが、ビブラートの出し方を身につける大切なポイントです。
ビブラートが歌唱にもたらす効果
ビブラートは、歌声に豊かさと表現力を与える重要な技術です。
声に温かみや感情を加えることで、楽曲の雰囲気や伝えたい気持ちをより強調できます。
また、音程を安定させ、長いフレーズを無理なく歌いやすくする効果もあります。
さらに、ビブラートは歌手の個性や特徴を表現する手段としても役立ちます。
自然なビブラートを使えばリラックスした状態で歌うことができ、聴き手にプロフェッショナルな印象を与えることが可能です。
このように、初心者が正しいビブラートの出し方を学ぶことで、歌に深みを加え、自分らしい歌声を磨いていけます。
ビブラートの種類と出し方

ビブラートには大きく分けて 横隔膜ビブラート・喉ビブラート・口(顎)ビブラート の3種類があります。
それぞれの方法で特徴や出し方が異なり、歌声に与える印象も変わります。
それぞれの特徴を理解し、曲調や歌詞に合わせて使い分けることで、歌に幅が生まれます。
自分に合ったビブラートの出し方を練習しながら習得し、表現力を高めていきましょう。
横隔膜ビブラート

横隔膜ビブラートはビブラートの基本であり、もっともコントロールしやすいビブラートの技法です。
横隔膜の収縮と弛緩を利用して息の流れを調整し、声に自然な揺らぎを加えます。
具体的には、腹筋を使って呼気をコントロールし、一定のリズムでお腹を押し出したり引っ込めたりすることで、ビブラートを生み出します。
この方法は喉に負担をかけにくいため、長時間の歌唱にも向いています。
また、声量や音色の変化が少なく、低音から高音まで幅広い音域で安定した効果を発揮できるのも大きな特徴です。
速さや幅を調整しやすいため、さまざまな曲調に対応できる汎用性があります。
横隔膜ビブラートを習得するには、まず腹式呼吸の練習が欠かせません。
腹式呼吸をしっかり身につけることで、より自然で美しい揺らぎをコントロールできるようになります。
ポップスやロックをはじめ幅広いジャンルで活用できるため、歌唱力を高めたい初心者にとって最もおすすめのビブラートの出し方です。
喉ビブラートの出し方
喉ビブラートは、声帯の振動を利用して音に揺らぎを与える歌唱技法です。
比較的習得しやすく、洋楽やロックなど力強い表現を求められるジャンルで多く使われています。
喉の奥を開いた状態を保ちながら、声帯の動きを微調整して揺らぎを作ります。

喉仏をこまかく上下させながら「あ〜〜〜〜」と歌ってみてください。
喉に力が入りすぎると「喉声」になってしまうので注意です!
練習方法としては、まず短い音から始め、徐々に持続時間を延ばしていきましょう。
息の流れを一定に保ち、声帯の振動を感じ取りながら少しずつ揺らぎの幅を広げていくと自然な喉ビブラートが身につきます。
喉ビブラートの出し方のポイントは、喉の筋肉をリラックスさせた状態で声帯の開閉をコントロールすることです。
喉に力を入れすぎると声が硬くなる原因にもなるので、リラックスした状態を意識して練習しましょう。
口または顎ビブラート
口や顎を上下に小刻みに動かして音の揺らぎを作るビブラートがあります。
比較的簡単に習得できる技法で、初心者にもおすすめです。
喉や横隔膜への負担が少ないため、無理なく練習できるのが特徴です。
声量や音色を変えずに、柔らかく揺らぎを加えられる点も魅力の一つです。練習時は顎をリラックスさせ、鏡を見ながら口の形や動きを確認しましょう。過度に大きな動きをすると不自然な音になってしまうため、動きを最小限にして速さと幅を調整することがポイントです。

顎を開けたり閉じたりしながら声を出すので「あうあうあうあうあう」という発声になるのが特徴的です。
演歌でよく使われる技法です。
口ビブラートや顎ビブラートを身につけると、喉への負担を抑えながら表現の幅を広げることができます。
ほかのビブラート技法(横隔膜ビブラートや喉ビブラート)と組み合わせることで、より多彩で魅力的な歌声を作り出せるでしょう。
初心者でもできるビブラートの出し方のコツ

ビブラートを上手に出すためには、正しい基礎と練習の積み重ねが大切です。
初心者の方は、次のポイントを意識して練習を進めましょう。
- 音程を正確に理解する
- ロングトーンを練習する
- 腹式呼吸をマスターする
- 喉をリラックスさせる
- 上手な人のビブラートを真似してみる
- 録音して自己評価する
基本をしっかり押さえて練習を続ければ、初心者でも徐々に自然なビブラートを出せるようになります。
焦らず、自分のペースで少しずつ習得していきましょう。
音程を正確に理解する

音程の安定=美しいビブラートの土台です。ビブラートは「中心となる音の周りで揺れる」表現なので、中心の音がぶれているとビブラート自体が不自然になります。
ビブラートは「中心音」周りの小さな揺れ。まず中心をピタッと取れることが最重要。ピアノやチューナーを使って、指定の音程を正確に出してみましょう。
以下の練習法を試してみましょう。
- ピアノやチューナーでターゲット音を鳴らし、その音にピッタリ合わせる練習を繰り返す。
- 小刻みな「スライド練習」:ターゲットより半音上→戻す、半音下→戻すをゆっくり繰り返す。
注意点:ビブラートは中心音の周りで揺れること。揺れが大きく中心がずれるようなら、まずは音程の安定を優先しましょう
ロングトーンを練習する
持続力とピッチの安定がビブラートの基礎です。
ロングトーンで声の芯がしっかりできると、声の揺らぎという遊びをコントロールしやすくなります。
ロングトーンのポイントは次の通りです。
- 喉ではなく腹筋でコントロールする感覚を大切に。
- ロングトーンの声が揺れてしまうときは、息が不安定になっているサインです。
以下の練習法を試してみましょう。
- 母音「ah/oo/ee」で1音をゆっくり一定に伸ばす(最初は無理せず短め→徐々に延ばす)。
- メトロノームを使い、一定の音量と音程を保つ練習(強弱をつける変化も取り入れるとコントロール力が上がる)。
ワンポイント:ロングトーン中に音程がぶれないことを基準に、そこから少しずつ揺らぎ(ビブラート)を入れていきます。
腹式呼吸をマスターする
腹式呼吸を身に付けると、安定した声と豊かな表現力を得ることができます。
胸ではなくお腹を使って呼吸することを意識し、横隔膜の動きを感じながら行いましょう。
息を吸うときは鼻から静かに吸い込み、お腹がふくらむように意識します。
吐くときは「スー」と音を立てながら、均一な息の流れを保つようにします。
吸う時間と吐く時間の比率は1:2(例:3秒吸って6秒吐く)を目安にすると、呼吸のリズムが安定します。
肩を上下させず、腹部の膨らみと収縮を感じながら行うのがポイントです。
日常生活の中でも腹式呼吸を意識的に行うことで、自然で美しいビブラートを出すための土台をつくれます。
喉をリラックスさせる

喉をリラックスさせることは、自然で美しいビブラートを出すために欠かせません。
喉が緊張していると、声が硬くなり揺れが不自然になります。
リラックスさせるためには、温かい飲み物を飲んで喉を温めたり、首や肩の筋肉を軽く伸ばしたりするのが効果的です。
あくびをするように口を開けて喉を広げたり、舌を前後に動かして喉の奥をほぐすのもおすすめです。
喉に手を当てて優しくマッサージすると、血行が促進されて筋肉のこわばりが取れやすくなります。
日々の練習の前後に喉をリラックスさせる習慣を取り入れることで、喉の負担を軽減し、より自然で滑らかなビブラートを出せるようになります。
上手な人のビブラートを真似してみる
ビブラートを上達させるには、上手な人の出し方を真似してみるのが効果的です。
特に演歌のビブラートは音の揺れが大きくわかりやすいため、初心者にもおすすめです。

カラオケで「津軽海峡冬景色」や「天城越え」をビブラート多めで歌うと気持ちいいですよ!
好きな歌手になりきって歌い、何度も繰り返すことで自然と体に感覚が染み込み、自分なりのビブラートを身につけられるようになります。
録音して自己評価する
録音して自分の歌声を聴き直すことは、ビブラートを上達させるうえで非常に重要です。
客観的に自分の歌を評価することで、感覚だけでは気づけない改善点を発見できます。
- 音の揺れ幅が均一かどうか
- ビブラートの速さが曲に合っているか
- 不自然に聞こえる箇所がないか
といったポイントを意識してチェックしましょう。
また、曲全体を通して「ここはビブラートをかけない方がいいな」という箇所に気づけることも大切な感覚です。
気づいた点はメモに残し、次回の練習で意識的に修正していくと効果的です。
録音を定期的に行い、過去の音源と聴き比べることで、自分の成長を確認できます。
さらに、信頼できる人や講師に聴いてもらいフィードバックをもらうと、客観的な意見から新たな課題が見つかりやすくなります。
ビブラートの練習におすすめの曲
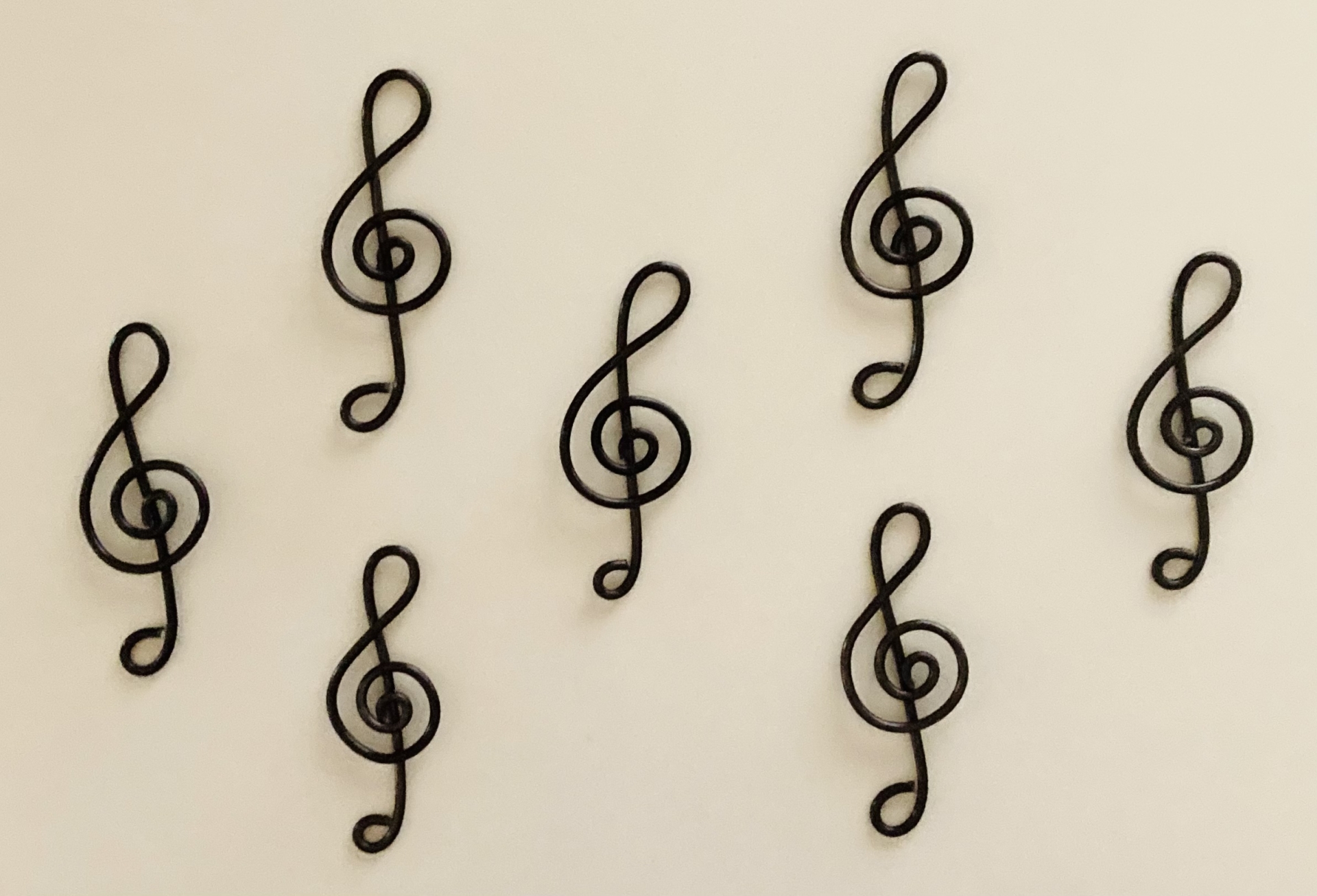
ビブラートの練習には、シンプルで音をしっかり伸ばせる曲を選ぶのが効果的です。
旋律が複雑すぎず、テンポがゆったりしている曲を選ぶことで、音の揺れ方や息のコントロールに集中できます。
練習曲を選ぶときのポイントは次のとおりです。
- メロディが単純で覚えやすい
- 長く伸ばす音(ロングトーン)が多い
- ゆったりとしたテンポで落ち着いて歌える
- 感情を込めやすく、表現の幅がある
特に、ビブラートを自然に使えるフレーズが多い曲を選ぶと上達が早まります。
演歌やゆったりしたバラードは、ビブラートを学ぶのにとても適しています。
「津軽海峡冬景色」や「天城越え」など聴き馴染みのある演歌を、ビブラートを大きくかけて思い切り歌ってみましょう。
そして、自分のレベルに合った曲から始め、慣れてきたら少しずつ難易度を上げていきましょう。
そうすることで、無理なく技術と表現力を磨いていけます。
ビブラートが出ないときの原因と対処法

ビブラートが出ない原因として多いのは、喉や体の力み、腹式呼吸の不足、そして音程の不安定さです。
喉に力が入り過ぎると声の振動が妨げられ、自然なビブラートがかかりません。まずは深い呼吸を意識し、喉や肩の力を抜いて発声しましょう。
また、腹式呼吸ができていないと息の流れが不安定になり、声が揺れづらくなります。呼吸練習を取り入れて安定した息を保つことが大切です。
音程が不安定な場合は、ロングトーンやスケール練習を通して音の安定感を養いましょう。
焦らず継続的に練習を重ねることで、自然で美しいビブラートが出せるようになります。
順番に見ていきましょう。
力み過ぎている
歌うときに体や喉に力が入り過ぎていると、ビブラートはうまく出せません。
喉や肩、首などが緊張すると、声帯や横隔膜の動きが硬くなり、自然な声の揺れが生まれにくくなります。
その結果、音程や音質が不安定になり、ビブラート自体が不自然なものになってしまうのです。
ビブラートは「海の波」のように表現されることが多く、その波形が不自然だと心地よく聴こえなくなります。
ビブラートを上手に出すには、自然な波形を生む必要があります。
そのためには、まず体全体をリラックスすることが大切です。
たとえば、
- 深呼吸して体の力を抜く
- 姿勢を正して、首や肩の力を抜く
- 無理にビブラートをかけようとしない
こうしたことを意識するだけでも、喉の緊張がやわらぎ、声が自然に揺れるようになります。
息の流れに身をまかせるように歌うと、無理のないビブラートが出せるようになります。
腹式呼吸を忘れている
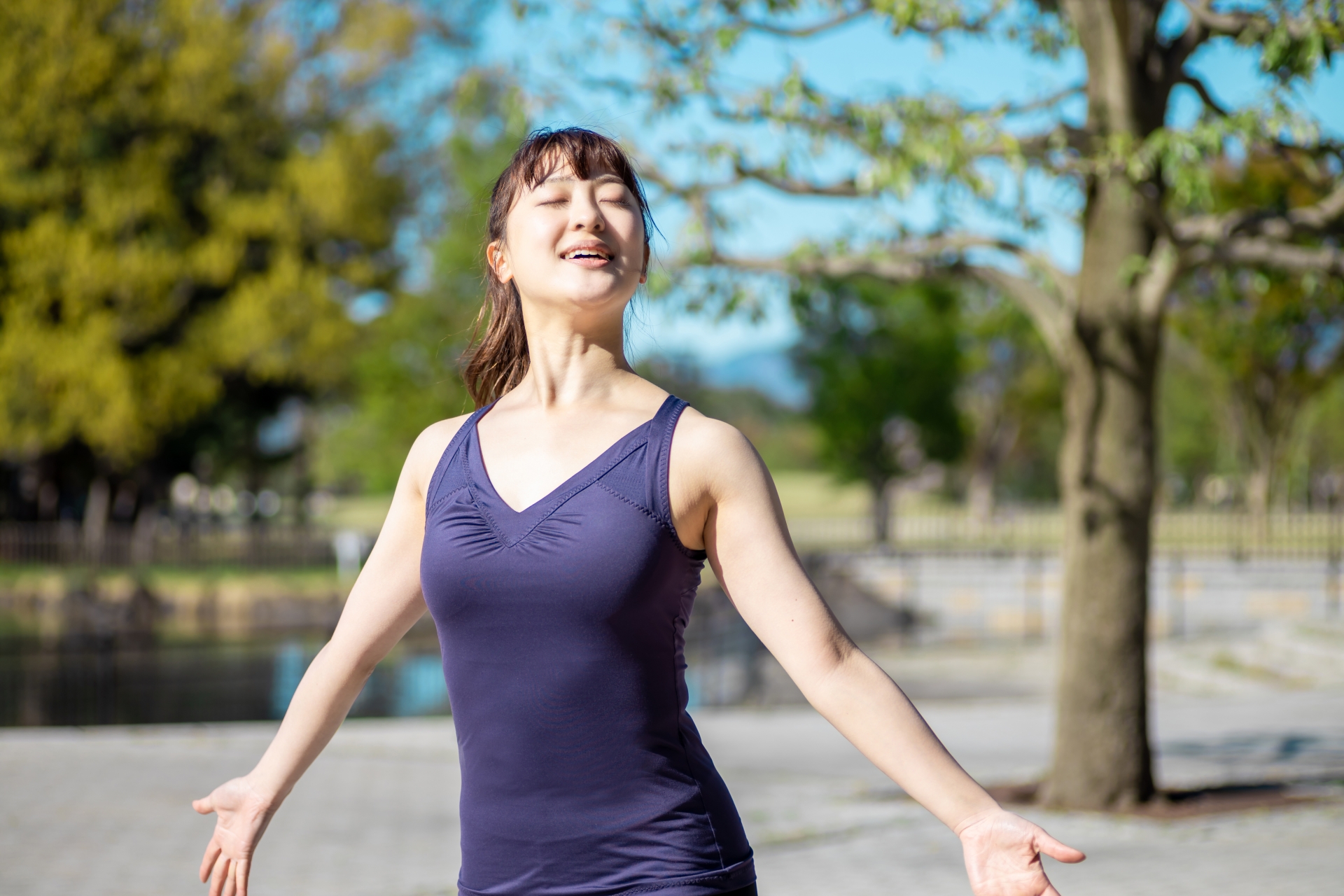
腹式呼吸を意識できていないと、ビブラートはうまく出せません。腹式呼吸は、安定した声と自然な揺らぎを支える基本です。

腹式呼吸は「横隔膜ビブラート」の項目で必須です。横隔膜ビブラートは「ビブラートの土台」なので、しっかり体に刻み込みましょう。
横隔膜をしっかり使うことで、声帯への負担を減らし、滑らかなビブラートを生み出すことができます。
腹式呼吸を忘れてしまうと、喉に力が入りやすくなり、音程がぶれたり、声量が落ちたりします。
歌うときだけでなく、普段の呼吸でもお腹の動きを意識することで、自然と腹式呼吸が身についていきます。
練習の際は、深く息を吸って、一定のスピードで吐き出す感覚をつかみましょう。
呼吸の深さや速さをコントロールできるようになると、ビブラートの幅や速さも自在に操れるようになります。
» 歌が上手くなる腹式呼吸の練習方法を解説
音程が不安定になっている
音程が安定していないと、ビブラートもうまくかかりません。
音程を正確に把握できていないと揺れの幅が不自然になり、聴き手に違和感を与えてしまいます。
ビブラートをきれいに響かせるには、まず音程を安定させることが大切です。
音程を安定させるためには、次の練習が効果的です。
- ピッチトレーニングで音の高さを正確に認識する
- 自分の歌を録音して聴き返す
- ロングトーンで安定した発声を身につける
ピアノやチューナーを使って音程を確認しながら練習すると、耳が鍛えられ、正確なピッチ感が自然と身につきます。
また、喉の緊張は音程のブレにつながるため、軽いストレッチや発声練習で喉をリラックスさせましょう。
腹式呼吸を意識して息を安定させれば、声の支えがしっかりし、自然なビブラートを出せるようになります。
焦らず、コツコツと練習を続けることが上達への近道です。
まとめ

ビブラートは、歌声に深みや表現力を加えるために欠かせないテクニックです。
ビブラートには、「横隔膜」「喉」「口・顎」を使った3つの方法があり、それぞれに特徴と出し方があります。
特に腹式呼吸と喉のリラックスは、自然で美しいビブラートを出すうえで重要なポイントです。
また、録音して自分の歌声を客観的に聴き返すことで、改善点を見つけやすくなります。
力み過ぎたり腹式呼吸を忘れたりすると、音程が不安定になりやすいため注意が必要です。
ビブラートは一朝一夕で身につくものではありませんが、焦らず継続して練習を重ねれば、自然で魅力的な揺らぎを表現できるようになります。
地道な練習を通じて、自分らしいビブラートを磨いていきましょう。